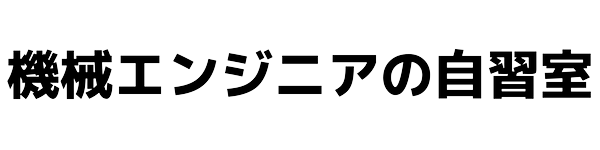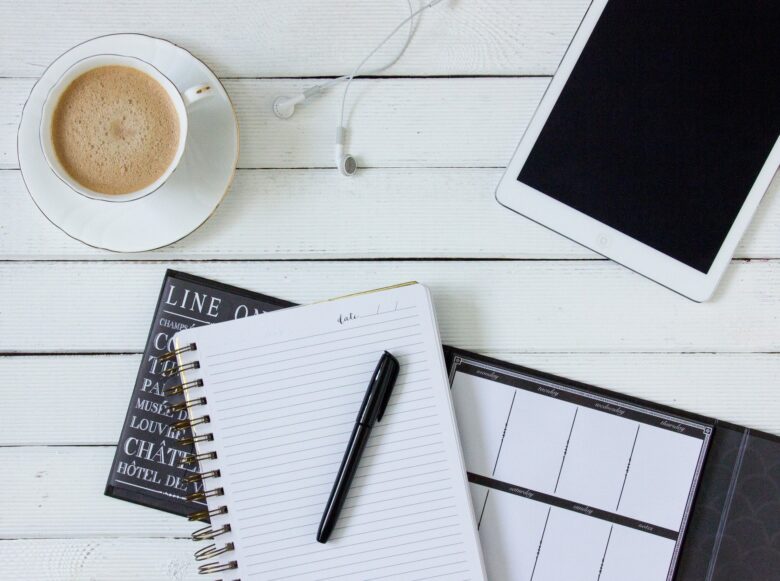どうも、ぜっとんです。
機械設計技術者試験2級の受験をして、結果がわかりました。
結論:不合格 でした。

今回は、不合格でしたが『受験体験記』として記事にします。
再挑戦する際の自己分析用もありますが、機械設計技術者試験というマイナー試験は受験体験記が少ないです。
そのため、これから受験する方に対しても残していこうと思います。
科目別5段階評価表
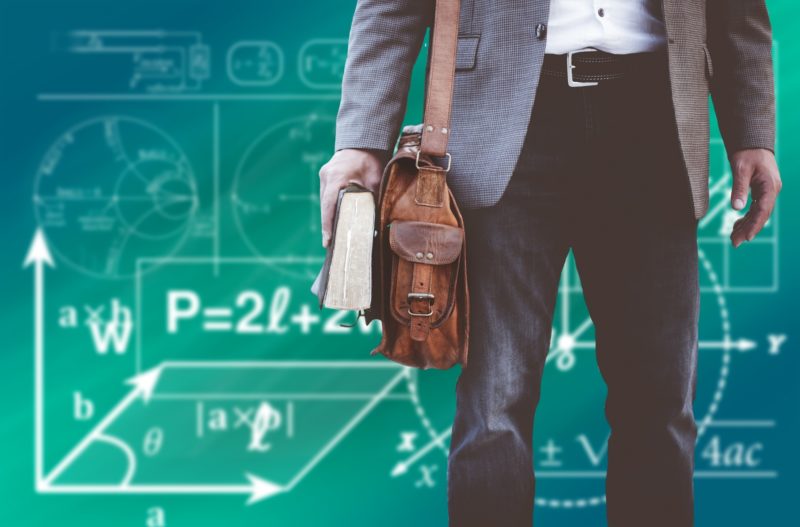
日本機械設計工業会のホームページには不合格者のみ確認できる科目別5段階評価表が搭載されます。
まずは結果を赤裸々に出していきます。
ただし注意があります。
令和3年度から2級科目は改定されます。
問題の難易度は従来レベルと変わることはないと案内されています。
出題傾向が変わると思いますので参考程度になります。
注意書きも終わりましたので、早速みていきましょう。


完全記述式の応用総合は完全に諦めていましたが、マークシート式の科目もボロボロでした。
恥ずかしい結果ですが、これで自分の苦手分野や得意分野がわかりました。
貴重なデータになりました。
機械設計技術者試験の勉強方法
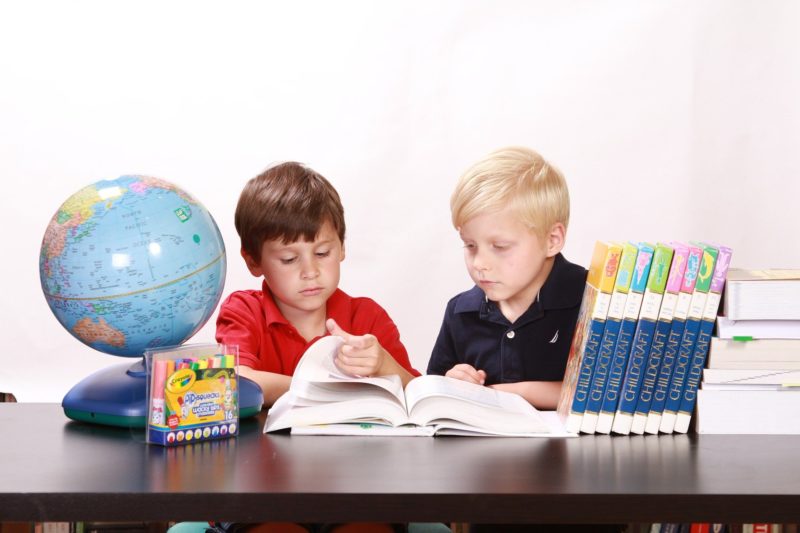
不合格になりましたが、実際にしていた勉強方法です。
ぼくの勉強方法はシンプルです。

朝に早起きしたり、仕事から帰ってきてから勉強していたのでシンプルな勉強方法にしようと決めていました。
材料力学、機械力学については2級、3級の問題も解いていました。
徹底的に「解き方」を身体に覚えさせようと思ったためです。
過去問を解いているときに気をつけていたポイントは下記にまとめます。
過去問で気をつけていたポイント
ポイント1:青色のボールペンで問題を解きまくる
ポイント2:答えを見てもわからなかった問題は諦める
ポイント3:計算するときは必ず単位も書く
ポイント4:キーワードをまとめておく
ポイント1:青色のボールペンで問題を解きまくる
黒色のボールペンではありません。「青色」が重要です。
青色には、ストレス低減と、集中力を高める効果があるからです。
これは、2014年に長岡技術科学大学の野村収作准教授が実験結果からの情報です。
また、ボールペンを使うことでインクの減り量をみて

という達成感を得ることができます。
そして、インク切れのボールペンを溜めていくことによって

と自信に繋がります。
青色ボールペン勉強法が気になる方は、ググってみてください。
いろいろと出てきます。
ポイント2:答えを見てもわからなかった問題は諦める
人間諦めも肝心です。
機械設計技術者試験は2級も3級も出題範囲が広すぎるため覚えることが多すぎます。
2級になると、実務で使われる知識に近いことを要求されます。
なので得意分野もあれば、苦手分野もあります。
苦手分野の勉強はモチベーションが続きません。

モチベーションを上げるためにぼくがやったことは、過去問の答えを見てもわからない問題はスッパリ諦めることです。
試験時間も限られているので、悩んだらムダだと判断しました。
解ける問題(得意分野)を解く時間を早くしたり、解ける問題(得意分野)を増やしたりすることでモチベーションを上げていました。
ポイント3:計算するときは必ず単位も書く
機械設計技術者試験の問題を実際に見た人は叫ぶはずです。

と。
様々な現場にいる設計者合わせるためだと思いますが、材料力学や機械力学の問題は単位や表記に一貫性がありません。
そのため、計算するときに単位を書いておかないと変な数字になります。
勉強中は解けた問題も、本番で緊張して凡ミスする可能性もありますので、単位を必ず書くクセを付けてました。
ポイント4:キーワードをまとめておく
機械設計技術者試験は他の資格試験とは異なり、過去問がそのまま出る確率が相当低いです。

ですが、科目によってはよく出てくるキーワードがあり、このよく出てくるキーワードに関連した問題や類似問題は多く出てきます。
環境安全は類似問題が出やすかったので、よく出てくるキーワードをまとめておくことで絞りやすくなります。
よく出てくるキーワードについては、別の記事で過去問分析の記事も出しています。
関連記事
機械設計技術者試験 3級の過去問分析できました
-

-
機械設計技術者試験 3級の過去問分析できました
どうも、ぜっとんです。 前回の記事で、機械設計技術者試験について紹介しました。 関連記事 【日本で唯一】機械設計に関わるエンジニアの資質を認定する試験。機械設計技術者試験について 日本機械設計工業会の ...
機械設計技術者試験 2級の過去問分析ができました
-

-
機械設計技術者試験 2級の過去問分析ができました
どうも、ぜっとんです。 前回ですが、機械設計技術者試験 3級について過去問分析をしました。 関連記事 機械設計技術者試験 3級の過去問分析できました 今回は、機械設計技術者試験 2級について過去問分析 ...
さいごに

不合格になってしまいましたが、貴重な経験ができました。
機械設計技術者試験2級の傾向が変わるためすぐに再挑戦することはありませんが、再挑戦したいと考えています。
しかし、ぜっとんの考えは
「資格試験はただの手段!どう活かしていくかは自分次第!」
です。
勉強することで、
「機械設計者として必要な知識を持ち、曖昧な設計をしない、させない」
に繋げたいです。
それでは!
電子書籍出版しました!
10年間の経験から学んだすべてを詰め込んだKindle本を出版しました。
いつでもどこでも読める電子版と気になる箇所をすぐに見返せるペーパーバック版をご用意しました。
未来の設計者のための貴重な教材です。お見逃しなく!
Kindle unlimitedに入っていると無料で読むことができます。
新規登録者は30日間無料で使えるので、まだの方は以下からどうぞ↓
あわせて読みたい
あわせて読みたい
現役機械エンジニアが答えます。機械設計技術者試験を受験する意味とは
-

-
現役機械エンジニアが考える 機械設計技術者試験を受験する意味とは?
どうも、ぜっとんです。 若手機械エンジニアや未経験から機械設計の仕事をする人が目標とする試験である『機械設計技術者試験』があります。 まずは『機械設計技術者試験』についてです。 マイナー試 ...